「市販品ミヤリサン」と「医療用ミヤBM」の酪酸菌の数の違い

市販品「強ミヤリサン」と医療用「ミヤBM」は、共にミヤリサン製薬が販売する酪酸菌(宮入菌)を主成分とした整腸剤。
便秘、下痢、ビオチン療法、潰瘍性大腸炎、アトピー治療、掌蹠膿疱症、乾癬などの治療に有効とされるが、その製品の主成分である宮入菌(酪酸菌)は、それぞれどれくらいの数の酪酸菌が含まれるのか。
実際にそれらを製造する「ミヤリサン製薬株式会社」に電話で問い合わせた結果が以下。
市販品「強ミヤリサン」の酪酸菌の数

市販品「強ミヤリサン」の菌数をメーカーに問い合わせた結果
9錠あたり「10の6乗~10の8乗」の酪酸菌(宮入菌)の数という説明と共に、100万から1億匹の酪酸菌が含まれるとの事。
市販ミヤリサンは、酪酸菌の数が100万から1億まで100倍の大きな差があるとの事で「なぜ酪酸菌の数に大きくバラつきがあるのでしょうか?」と尋ねると、製造方法によってどうしても安定的な菌の数にはならないという返答。
医療用レベルに菌数の安定性を高めようとすると、市販医薬品として製造コストが高くなってしまうと思われる。
医療用「ミヤBM錠」の酪酸菌の数

宮入菌(酪酸菌)を含む市販「強ミヤリサン」は、医療用医薬品として「ミヤBM錠」と「ミヤBM細粒」の2種類が調剤薬局で販売されている。基本的に医師の処方箋が必要。
その医療用では市販品と酪酸菌の菌数が違う。まずは錠剤タイプから。
錠剤タイプ「医療用ミヤBM」の菌数

「医療用ミヤBM錠」の菌数をメーカーに問い合わせた結果
2錠あたり1000万から1億個、1錠あたりでは500万~5000万の酪酸菌(宮入菌)が含まれるとの事。市販品である強ミヤリサンは100万から1億までの100倍の差があったが、医療用ミヤBM錠剤タイプは10倍の幅がある。
なぜ菌の数に10倍のバラつきがあるかというと「製造方法によるもの」と回答。厳格な品質が求められる「医療用」なので、市販品の強ミヤリサンよりも酪酸菌の含有数に差がないと思われる。
なお、ビオチン治療において、ビオチン摂取と共に「ミヤBM 2錠」の同時摂取が必要と言われるのは、この医療用ミヤBM錠剤の2錠の事であり、市販品の「強ミヤリサン 2錠」の事ではない。Web上には間違った記述・説明をしている情報サイトが多いので注意。
医療用「ミヤBM細粒」の酪酸菌の数

ミヤBM細粒の宮入菌(酪酸菌)の数をメーカーに問い合わせた結果
ミヤBMの細粒は、例えば1000万から1億といった差があるわけではなく、ほぼ1億の宮入菌(酪酸菌)が配合されているという。
これは製造方法により、ほぼ1億の菌数に調整できるのだそう。「錠剤」と「細粒」の違いで、菌数の安定性に違いがある。
市販品でも医療用でも効果は変わらない
一般に、市販品よりも多くの酪酸菌が含まれる医療用ミヤBMを服用したほうが効果があるように思う。
そのあたりをミヤリサン製薬に対して「酪酸菌の配合数が違う市販品と医療用に効果の違いがあるのでしょうか?」と質問すると「細菌学の考え方では、ほとんど効果は変わらない」という回答をもらった。
腸内において細菌どうしは常に勢力争いをしており、そこに新たな酪酸菌が投入される事で、良い腸内フローラに変化していく事になり、その投入された酪酸菌が100万個から1億個レベルの数の範囲であれば、大きな差はないのだという。
つまり、市販品でも医療用でも最終的な効果は同じという事だが、しかし菌数が多いほど腸内フローラの変化がより顕著になるのは間違いないはず。なお、酪酸菌の服用だけで腸内フローラが絶対に良くなるというわけではない。
ミヤリサン服用は効果があるの?
そもそも酪酸菌は、通常はヒトの腸内に兆単位で存在している菌。ヒトの腸内には約100兆個の腸内細菌が存在しているとされ、そのうち酪酸菌は腸内細菌全体の5%ほど、多い人は10%以上の酪酸菌が存在しているとされる。
つまり、ヒトの腸内には5兆個前後、多い人は10兆個ほどの酪酸菌が存在するが、そこに100万個から1億個レベルのミヤリサン(ミヤBM)を服用したとしても、ほとんど効果が無いように思えてしまう。
実際に、お医者さんの中でも1億匹レベルの酪酸菌(ミヤBM)を服用する事に対して懐疑的な見解をもつ人がいたりする。しっかりと食物繊維を摂取し、腸内にしっかりと酪酸菌が存在していれば、ミヤBMを服用する必要はないかもしれない。
しかし、アトピー性皮膚炎、潰瘍性大腸炎、掌蹠膿疱症、乾癬などの治療において、ミヤBMを服用する事で症状が改善に向かうケースが多いのも事実。特に、掌蹠膿疱症性の関節炎の場合はビオチンによる治療効果が高いとされる。
また、ビオチン治療においてはミヤBMを服用する事で血中ビオチン濃度が安定に向かうようになる事もわかっている。服用中断の判断は難しいが、特に人体に副作用がある薬ではないため、症状予防のために続けるのが無難かも。
酪酸菌を増やす食品
一般に善玉菌を育てる食物繊維というと「野菜」「果物」というイメージ。当然、それらも最終的に酪酸菌の増加につながるが、「酪酸菌の増加」だけに限って言えば海藻類や穀物に含まれる食物繊維が重要視されるようになってきた。
海藻類
昆布、ワカメ、もずく、ひじき、海苔などの海藻類に含まれる「アルギン酸」という水溶性食物繊維は、腸内に存在する「ロゼブリア菌」「ラクノスピラ菌」「コプロコッカス菌」などの酪酸菌のエサになりやすい。
一般に、水溶性食物繊維は早い段階で腸内細菌のエサになるため、大腸(腸の奥)に存在する酪酸菌のエサになる前に、他の腸内細菌に利用されてしまうケースが多い。
しかし、海藻に含まれるアルギン酸は腸内細菌による分解性が25%レベルと低いため、大腸にまで届いて酪酸菌に利用されやすい。(水溶性食物繊維で有名なイヌリンやペクチンなどの腸内細菌利用性は100%レベルだが、アルギン酸の腸内細菌利用性は低い)
特に「ロゼブリア菌」は海藻を食べる日本人の腸に多く存在する酪酸菌だとされ、日本人が長寿である要因ではないかと考える研究者もいる。
最もコスパが良いのが「乾燥わかめ」。お味噌汁やお吸い物を食べる時、乾燥ワカメを多めに加えたいところ。
穀類
小麦やお米などの穀類、じゃがいも、さつまいもなどに含まれる「レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)」という不溶性食物繊維や、小麦全粒粉、玄米などに含まれる「アラビノキシラン」という不溶性食物繊維も腸内細菌の分解が遅い事から腸の奥にまで届いて酪酸菌のエサになりやすい。
まとめ
「強ミヤリサン」「ミヤBM」などの医薬品は補助的に活用し、基本はバランスの良い食生活が基本。他にも、喫煙、飲酒、甘い食べ物の取りすぎ、ストレスなども腸内環境とビオチン治療にとってマイナスなので注意。
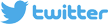



 SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移
トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移 強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い
強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移
テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移 東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移
東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移 マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況
マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況 現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移
現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移 ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移
ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数
ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数 TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移
TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移 楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移
楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移 NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況
NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況 Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移
ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移 Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移
Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移 フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移
フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移 ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率
ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率 任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数
任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数 日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移
日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移 インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移
インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移 BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移
BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況
Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況 メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率
メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率 LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況
LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況 キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明!
キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明! コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移
コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移 【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング
【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング 大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移
大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移 Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア
Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件
ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件 韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較
韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較 サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率
サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率 岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る
岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る