スポンサーリンク
東芝半導体事業からキオクシアまでの売上推移
まずはキオクシアの前身である東芝時代の半導体部門(電子デバイス部門)の決算推移から。
| 年度 | 売上高・収益 | 営業利益 [営業利益率(%)] |
|---|---|---|
| 1999年 | 1兆3732億円 | -235億円 [-1.7%] |
| 2000年 | 1兆5513億円 | 1163億円 [7.4%] |
| 2001年 | 1兆748億円 (ITバブル崩壊) (東芝はDRAMから撤退) |
-1763億円 [-16.4%] |
| 2002年 | 1兆2960億円 | 305億円 [2.3%] |
| 2003年 | 1兆2836億円 | 1170億円 [9.1%] |
| 2004年 | 1兆3072億円 | 925億円 [7.0%] |
| 2005年 | 1兆3881億円 | 1233億円 [8.8%] |
| 2006年 | 1兆6573億円 | 1197億円 [7.2%] |
| 2007年 | 1兆7385億円 | 741億円 [4.2%] |
| 2008年 | 1兆3249億円 | -3232億円 [-24.3%] |
| 2009年 | 1兆3139億円 | -288億円 [-2.1%] |
| 2010年 | 1兆7578億円 | 711億円 [4.0%] |
| 2011年 | 1兆6162億円 | 901億円 [5.5%] |
| 2012年 | 1兆2802億円 | 464億円 [3.6%] |
| 2013年 | 1兆6873億円 | 2468億円 [14.6%] |
| 2014年 | 1兆7688億円 | 2166億円 [12.2%] |
| 2015年 | 1兆6049億円 (東芝の不正会計発覚) |
-1016億円 [-6.3%] |
| 2016年 | 1兆7002億円 (東芝は米WH問題で債務超過へ) |
2470億円 [14.5%] |
| 2017年 | 2兆64億円 | 5196億円 [25.8%] |
出所:東芝。本決算期は3月末。セグメントにおける「電子デバイス部門」の成績。東芝時代はパワー半導体やシステムLSIなどのNANDフラッシュメモリ以外の半導体事業の成績も含まれている事に注意。
そして、2017年に債務超過に陥った東芝からメモリ事業だけが分離して「東芝メモリ」となり、その後に「キオクシア」が誕生。その業績が以下。
| 年度 | 売上高・収益 | 営業利益 [営業利益率(%)] |
純利益・最終損益 [純利益率(%)] |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 1兆2639億円 | 1163億円 [9.2%] |
605億円 [4.8%] |
| 2019年 | 9872億円 | -1731億円 [-17.6%] |
-1667億円 [-16.9%] |
| 2020年 | 1兆1785億円 | 66億円 [0.5%] |
-245億円 [-2.0%] |
| 2021年 | 1兆5265億円 | 2162億円 [14.2%] |
1059億円 [6.9%] |
| 2022年 | 1兆2821億円 | -990億円 [-7.7%] |
-1381億円 [-10.8%] |
| 2023年 | 1兆766億円 | -2527億円 [-23.5%] |
-2437億円 [-22.6%] |
| 2024年 | 1兆7064億円 (12月 株式上場) |
4517億円 [26.5%] |
2723億円 [16.0%] |
出所:KIOXIA。本決算期は3月末。キオクシアになるとメモリだけになった事で東芝時代よりも売上高が減少している事に注意。
スポンサーリンク
平均利益率
東芝半導体時代の1999年から2017年までの営業利益率の平均が4.0%。キオクシアとなった2018年から2024年までの営業利益率の平均が0.2%。
- 出資会社
- 東芝の業績推移
会社の動向
- 2001年、ITバブル崩壊で営業損益「-1763億円」の大赤字。この年に東芝はDRAMから撤退を発表。その後はNANDフラッシュメモリに注力。
- 2017年度に高利益を出しているのは、Amazon、マイクロソフト、アップル、Google、フェイスブックなどのデータセンターが競うように設備投資を進めた事が影響。特に5Gを見越してGoogle(YouTube)の設備投資が急増。
- 2019年度の赤字は、GAFAMの設備投資が一服し、在庫を抱えてしまったことが影響。また、独立費用も要因。
- 2020年度は、コロナ問題や米国による中国ファーウェイ輸出規制があったが、それでも営業利益は黒字を確保。
- 2020年度の最終損失が-245億円の赤字だが、これは東芝メモリからの独立にともなうコストとされる。(出所:キオクシア)
スポンサーリンク
KIOXIAの財政・経営状況
| 年度 | 総資産 [現金・手元資金] |
負債総額 [有利子負債] |
自己資本・純資産 [自己資本比率(%)] |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 2兆8202億円 [2571億円] |
1兆9541億円 [8307億円] |
8662億円 [30.7%] |
| 2019年 | 2兆7184億円 [2170億円] |
2兆192億円 [1兆2744億円] |
6992億円 [25.7%] |
| 2020年 | |||
| 2021年 | 3兆682億円 [4698億円] |
||
| 2022年 | 2兆9744億円 [2613億円] |
||
| 2023年 | 2兆8649億円 [1875億円] |
2兆4152億円 [1兆2942億円] |
4497億円 [15.7%] |
| 2024年 | 2兆9196億円 [1679億円] |
2兆1820億円 [9995億円] |
7376億円 [25.3%] |
出所:KIOXIA、2019年まではキオクシア決算公告。2021年からは決算短信、有価証券報告書。
- 数千億円単位の多額の設備投資額が毎年必要となるメモリ業界において、財務状況は厳しいというのが実情。
- しかし、近年は経済安全保障を理由として半導体メーカーに政府補助金が投入されるようになっているため、キオクシアがあっさりと倒産するような事はないはず。
- 2025年3月期は通期で26.5%の営業利益率を残し、財務改善に向かう。
連結社員数と研究開発投資について
| 年度 | 従業員数(連結) | 平均年収 | 設備投資費 | 研究開発費 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 15042人 | 1148万円 | 2256億円 | 1328億円 |
出所:キオクシア。平均年収は有価証券報告書における提出会社の数値。
スポンサーリンク
ライバルとの比較
キオクシアのライバル関係にある韓国サムスンやSKハイニックス、米国マイクロンの財務状況を確認。
| 経営状況 | サムスン | SKハイニックス | マイクロン |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 42.6兆円 | 9.63兆円 | 6.47兆円 |
| 負債総額 | 12.17兆円 | 3.42兆円 | 1.64兆円 |
| 自己資本・純資産 | 30.49兆円 | 6.21兆円 | 4.83兆円 |
| 自己資本比率 | 71.5% | 64.4% | 74.6% |
| 株式時価総額 (2022年4月) |
約46兆円 | 約8.2兆円 | 約8.8兆円 |
韓国1ウォン=0.1円、1ドル=110円で換算。
- キオクシアの自己資本比率が25%程度の中、サムスン、SK、マイクロンは60%~70%を超える。
- サムスン、SK、マイクロンは近年寡占化してしまったDRAM市場で爆発的に利益を出してきた企業なので、財務状況もかなり安定している。
- 日本がDRAM(エルピーダメモリ)を諦めるというのは、どこかの企業が大きくなることを意味するが、大きくなったのがライバルの韓国となった形。今頃言っても仕方ないがエルピーダは売却すべきではなかった。
生産額と市場シェアの推移
キオクシアの四半期ベースの推移をサムスンやSKハイニクスなどの大手と比較。
| 企業 | 2020年10-12月期 | 2021年10-12月期 | 2022年10-12月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高・収益 [市場シェア(%)] |
|||
| 1位(韓国) サムスン電子 |
46.43億ドル [32.9%] |
61.09億ドル [33.1%] |
34.80億ドル [33.8%] |
| 2位(日本) キオクシア |
27.48億ドル [19.5%] |
35.42億ドル [19.2%] |
19.68億ドル [19.1%] |
| 3位(韓国) SKハイニックス |
28.45億ドル [20.2%] |
36.10億ドル [19.5%] |
17.55億ドル [17.1%] |
| 4位(米国) ウエスタンデジタル |
20.33億ドル [14.4%] |
26.19億ドル [14.2%] |
16.57億ドル [16.1%] |
| 5位(米国) マイクロン |
15.73億ドル [11.2%] |
18.77億ドル [10.2%] |
11.03億ドル [10.7%] |
| その他 | 2.51億ドル [1.8%] |
7.17億ドル [3.9%] |
3.23億ドル [3.1%] |
出所:トレンドフォース。市場シェアは金額ベース。SKハイニックスは買収したインテルNAND事業と合計した数字。
- SKハイニックスがインテルNAND事業(Solidigm)を買収した事でシェアを拡大。キオクシアと2位~3位争い。
- キオクシアとウエスタンデジタルは協業関係であり、すべて日本国内(三重県四日市+岩手県北上市)で生産。日本の半導体産業の生態系を維持する重要なボリューム。
- 韓国勢のサムスンとSKハイニックスは共に、NANDメモリの40%前後を中国で生産。メーカー基準ではなく製造国基準で言えば、NANDフラッシュメモリ製造量で日本と韓国に大きな差はない。
キオクシアは大丈夫!
日本の半導体産業というと、かつて10社以上もあったDRAM企業がすべて消失しただけあって、どうしても悲観してしまいがち。しかし、キオクシアはかつてのDRAM企業のような失敗はしないと断言したい。
競争に負けない理由
- かつてDRAM企業は日本だけで10社以上があり、日本企業だけの競争で疲弊してしまっていた。一方、NANDメモリはキオクシアの1社だけで日本企業どうしの競争はない。
- NAND市場は5~6社の寡占で競争はやや少ない業況。投資ベースの競争で言えば、キオクシアWD連合、サムスン、SKハイニクス、マイクロン、中国YMTCの5大勢力。
- NANDフラッシュメモリはデータ社会が進むだけ安定的な需要が期待できる。つまり極端な値崩れを起こしにくく、かつてのDRAM業界にみられた巨額赤字を出してしまうような事態にはなりにくい。
- 最も力強い需要が期待できるデータセンター向けストレージが、総合的な運用コストを削減する目的でHDDからSSD(NANDメモリ)を採用するようになっていく。
- NANDフラッシュメモリは性質的に寿命があるので、データセンターでは定期的に新品との交換が必要。つまり継続的に巨大需要が期待できる。
- NANDメモリを必要とする企業は、DRAM業界のような「寡占化」→「価格が高止まり」という状況を嫌うので、財務的に弱いキオクシアを優先してくれる状況。例えばアップルやDELLがキオクシアに出資してくれているのもその理由。
- iPhoneやiPadといったアップル製品に搭載されるNANDメモリにおいてもキオクシアが第一サプライヤー。
- 中国のスマホメーカーは、ライバルのサムスンをサプライチェーンから外したい事情があり、キオクシアを優先してくれている状況。
エルピーダと比較して財務面でも大丈夫な理由
- 日本のDRAM産業は1986年から1996年までの日米半導体協定による制裁の影響をもろに受けた。一方、キオクシアはそういった制裁を意識する必要はない。
- エルピーダメモリが倒産した2012年は、当時の日銀白川方明総裁は積極的な金融政策をしなかったため、円高と株価低迷が続き、エルピーダも破綻。一方、現在の日銀はインフレ2%成長目標に向けた「金融政策ルール」が出来上がっており、今後は継続的な量的緩和によって為替市場も株式市場も安定。これによりキオクシアの経営や財務状況も少なからず恩恵を受ける。
- 倒産したエルピーダは、序列が生じないままNECと日立を統合したことで主導権争いが生じ、発足からしばらくは生産性が悪い状況が続いた。一方、キオクシアはエルピーダのような混乱は起きない。
- 半導体産業の重要性が認識されるようになり、自民党内に半導体復興をかかげる「半導体戦略推進議員連盟」が発足。キオクシアと連携することに。日本政府や官民ファンドからの積極的な支援(補助金&出資金)が約束される。
- エルピーダはメインバンクをもたなかったため資金繰りが困難になった。一方、キオクシアはメインバンクをもち、経営難になっても将来性が高い事から融資を受けやすい状況。
- 2021年の銀行法改正により、銀行から融資の他に5%以上の出資も受けることができるようになった。財務問題が発生したら「メガバンク出資のもとで再建」というような事もありえる。
MRAMでゲームチェンジャーへ
キオクシアは、サムスンやSKハイニックスなどがもつDRAMビジネスを持っていない。そのため、製品ポートフォリオが弱く、大口顧客との商談も不利になる。
そんな中、キオクシアはDRAMの代わりになるMRAM(エムラム)という次世代メモリの開発を進めており、世界的にもリードしている状況。
DRAMは、データ保持のために電気を通し続ける必要があるため電力消費が高い。その欠点をカバーする存在が、次世代不揮発性メモリのMRAMで、電力消費を大幅に抑える事が可能。
MRAMは、もう少し技術開発が必要とはいえ、いずれキオクシアは日本がDRAMで敗北した雪辱を果たしてくれるはず。
韓国勢には負けてはいけない
NANDフラッシュメモリは東芝が開発し、韓国に供与した技術。その与えた側の日本が韓国に負ける事などあってはならない。
師匠が弟子に負けていいのは亀仙人だけ。総動員してでもキオクシアを死守すべし。
スポンサーリンク
関連記事
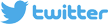









 SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移
トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移 強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い
強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移
テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移 マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況
マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況 現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移
現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移 ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移
ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数
ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数 TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移
TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移 楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移
楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移 NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況
NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況 Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移
ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移 Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移
Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移 フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移
フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移 ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率
ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率 任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数
任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数 日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移
日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移 インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移
インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移 BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移
BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況
Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況 メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率
メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率 LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況
LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況 キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明!
キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明! コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移
コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移 【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング
【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング 大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移
大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移 Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア
Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件
ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件 韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較
韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較 サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率
サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率 岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る
岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る