CATLの連結決算:通年の売上推移
| 年度 | 売上高・収益 | 営業利益 [営業利益率(%)] |
純利益・最終損益 [純利益率(%)] |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 57.03億元 (1140億円) |
10.45億元 (209億円) [18.3%] |
9.31億元 (186億円) [16.3%] |
| 2016年 | 148.79億元 | 32.12億元 [21.6%] |
28.52億元 [19.2%] |
| 2017年 | 199.97億元 | 48.32億元 [24.2%] |
38.78億元 [19.4%] |
| 2018年 | 296.11億元 | 44.83億元 [15.1%] |
35.79億元 [12.1%] |
| 2019年 | 457.88億元 | 57.59億元 [12.6%] |
45.60億元 [10.0%] |
| 2020年 | 503.19億元 | 69.59億元 [13.8%] |
55.83億元 [11.1%] |
| 2021年 | 1303.56億元 | 198.23億元 [15.2%] |
159.31億元 [12.2%] |
| 2022年 | 3285.93億元 | 368.22億元 [11.2%] |
307.29億元 [9.4%] |
| 2023年 | 4009.17億元 | 537.18億元 [13.4%] |
441.21億元 [11.0%] |
| 2024年 | 3620.12億元 (7兆2402億円) |
640.51億元 (1兆2810億円) [17.7%] |
507.44億元 (1兆148億円) [14.0%] |
平均利益率
- バッテリー競合の業績推移
- パナソニックエナジー
- LGエナジー
- サムスンSDI
会社の動向
- CATL(寧徳時代新能源科技:ねいとくじだいしんのうげんかぎ)は、2011年12月設立の中国のバッテリーメーカー。日本の電子部品メーカーTDKの社員たちが駐在先の香港で起ち上げたATLからスピンオフしてCATLは誕生。
- 中国の中央政府や地方政府からの多額の補助金などにより急成長。
- 2017年に車載バッテリー分野で日本のパナソニックを抜き世界トップシェアへ。
- CATLの営業利益率は業界内でも高く、2021年度は15.2%の利益率。比較として、2021年度のパナソニックエナジーの営業利益率が8.4%、韓国LGエナジーが4.3%、韓国サムスンSDIが7.8%。
- 2024年度は売上高が減少。世界中でEVが下火になっている根拠。
財政・経営状況
| 年度 | 総資産 [現金・手元資金] |
負債総額 [有利子負債] |
自己資本・純資産 [自己資本比率(%)] |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 86.73億元 [12.93億元] |
71.75億元 [18.99億元] |
14.98億元 [17.3%] |
| 2016年 | 285.88億元 [24.57億元] |
127.97億元 [17.69億元] |
157.91億元 [55.2%] |
| 2017年 | 496.63億元 [140.81億元] |
231.92億元 [47.39億元] |
264.71億元 [53.3%] |
| 2018年 | 738.84億元 [277.31億元] |
386.84億元 [46.72億元] |
352.00億元 [47.6%] |
| 2019年 | 1013.52億元 [340.60億元] |
591.64億元 [71.06億元] |
421.88億元 [41.6%] |
| 2020年 | 1566.18億元 [717.12億元] |
874.24億元 [124.03億元] |
691.95億元 [44.2%] |
| 2021年 | 3076.67億元 [904.36億元] |
2150.45億元 [342.42億元] |
926.22億元 [30.1%] |
| 2022年 | 6010.52億元 [1930.25億元] |
4241.43億元 [735.15億元] |
1769.09億元 [29.4%] |
| 2023年 | 7171.68億元 [2643.14億元] |
4972.85億元 [986.29億元] |
2198.83億元 [30.7%] |
- 中国政府からの補助金のもとで工場建設や設備投資が急伸。総資産規模の拡大ペースが早い。
- CATLの財務問題は一切なし。経営難になったとしても「経済安全保障」を理由として中国政府から補助金が入るはず。
- 2025年3月時点のCATLの株式時価総額が1.14兆元。日本円で約23兆円。
連結社員数と開発投資について
| 年度 | 全従業員数 | 開発エンジニア数 | 研究開発費 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 1万4712人 | 3425人 | 16.32億元 |
| 2018年 | 2万4879人 | 4217人 | 19.91億元 |
| 2019年 | 2万6779人 | 5364人 | 29.92億元 |
| 2020年 | 3万793人 | 5592人 | 35.69億元 |
| 2021年 | 8万3573人 | 1万79人 | 76.91億元 |
| 2022年 | 11万8878人 | 1万6322人 | 155.10億元 |
| 2023年 | 11万6055人 | 2万604人 | 183.56億元 |
車載バッテリーシェアの推移
| 企業 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| CATL(中) | 28% | 26% | 28% | 37.0% |
| LGエナジー(韓) | 13% | 25% | 23% | 13.6% |
| BYD(中) | 8% | 6% | 7% | 13.6% |
| パナソニック(日) | 22% | 17% | 15% | 7.3% |
| SKオン(韓) | 3% | 6% | 5% | 5.4% |
| サムスンSDI(韓) | 6% | 7% | 6% | 4.7% |
| CALB(中) | 1% | 2% | 2% | 3.9% |
| Guoxuan(中) | 3% | 2% | 2% | 2.7% |
| EVEエナジー(中) | 1%未満 | 1%未満 | 1%未満 | 1.8% |
| SVOLT(中) | 1%未満 | 1%未満 | 1%未満 | 1.4% |
| AESC(中) | 3% | 2% | 2% | |
| Sunwoda(中) | 1%未満 | 1%未満 | 1%未満 |
- 中国企業全体の車載バッテリーシェアは、2021年度では40%以上。2022年度は60%以上に上昇。
- 韓国勢のシェアは2021年度は34%だったが、2022年度には23.7%に低下。
- 日本の最高位はパナソニック。市場シェアを落とし続けているが、これはCATLやLGエナジーなどと比較して投資規模が低いため。しかし、和歌山やアメリカの工場が完成し、生産が波に乗ればシェアが上がってくるはず。
- 日本の車載バッテリーのサプライヤーは、パナソニック、GSユアサ、東芝、ビークルエナジー(旧日立系で日産が買収)など。
- 自動車メーカーとの合弁で言えば、トヨタとパナソニックの合弁企業(PPES、PEVE)や、ホンダとGSユアサの合弁企業(ブルーエナジー)、日産が20%を残して中国企業に売却したエンビジョンAESCなど。
- アメリカやヨーロッパメーカーはランキングに存在しない。現状の動向では、市場トップ5に入り込むような欧米メーカーは登場しないと予想できる。
なぜ中国バッテリーは安いのか
中国はバッテリー産業に力を入れている。バッテリーはエネルギー産業でもあり、つまり、中国は自動車産業と共に世界のエネルギー産業で世界的な主導権を取ろうとしている。
その中国産バッテリーはなぜ安いのか。価格競争の優位性は以下。
- リチウム鉱山というと、中国、豪州、チリ、アルゼンチンの4ヵ国に集中。
- その中でも中国のリチウム価格は特に安いが、その理由は安い人件費と、水質汚染や土壌汚染などの環境汚染に対する配慮が欠けているため。
- 中国政府からの工場建設や電気代、水道代などについて多額の補助金がある。工場建設や設備投資だけではなく、生産における電気代や水道代などにおいてもサポートがある。これはディスプレイ分野などと一緒。
中国は、自分達の土地を犠牲にしてでもバッテリーシェアと中国製電気自動車で世界シェアを確保したい。
主要顧客
- アメリカメーカー……テスラ、ゼネラルモーターズ、フォード。
- ドイツメーカー……フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツ。
- その他の欧州メーカー……ステランティス、ルノー。
- 日本メーカー……トヨタ、ホンダ、日産、マツダ、ダイハツなど。
- 韓国メーカー……ヒョンデ、キア。
- 中国メーカー……北京汽車、吉利汽車、宇通客車、中通客車、金龍客車、上海汽車、福田汽車など。
CATLの顧客は、実質的に世界中の自動車メーカーとなる。中国では政府のEV補助金を受けたいのならば、中国政府の認定したメーカーのバッテリーを積むことが義務付けられている。
中国は世界最大の自動車市場。コロナ前の2019年度の中国自動車市場規模は2576万台。比較としてアメリカが1705万台、ヨーロッパが1560万台、日本が527万台。
世界の自動車メーカーが中国市場に依存している状況。つまり、中国で自動車を売りたい企業ならばCATLのような中国メーカーと協力関係を結ぶ必要があり、それがCATLのバッテリートップシェアを確実にしている大きな理由。
電動バイクや蓄電池はTDKと合弁
2022年6月、中国CATLは日本のTDK完全子会社ATLと合弁企業を設立。主なビジネスは家庭用蓄電システムや電動二輪車の開発と製造販売。合弁会社は2社。
- Xiamen Ampcore Technology Limited……リチウム電池の「バッテリーセル」の開発と製造。出資比率は、CATL70%、ATL(TDK)30%。
- Xiamen Ampack Technology Limited……「電池パック」の製造。パッケージ化。出資比率は、CATL30%、ATL(TDK)70%。
CATLは、スケールメリットを活かし、車載電池だけではなく電動バイク、家庭用・産業用の蓄電システム分野の拡大を見込む。
CATLがTDKと組んだ理由としては、二輪向けでは日本のバイクメーカー(ホンダ、スズキ、ヤマハ、カワサキなど)へのビジネスを強化したいため。そして、蓄電池では日本市場へのビジネス拡大を考えているため。
日本資本が入っていないと日本市場からCATLが排除されてしまう。中国資本が入っていないと、TDKは中国市場から排除されてしまう。結果として両社で利益をシェアする形となった模様。
バッテリー産業は、石油や天然ガスなどと同じようなエネルギー産業の一つであり、日本はその分野を完全自前主義としたいところ。しかし、リチウムの権益や経済安全保障を考慮すれば、相互依存状態を形成した方が総合的なメリットがある。
なお、「バッテリーセル」の製造のほうが開発コストや設備投資がかかる中核的な存在であるため、セル製造開発会社の70%を出資するCATLの方がTDKよりも主導権がある形といえる。結局は「お金の話し」という事。
会社の歴史
2001年iPodが販売開始された年。ATLは、iPod向けのバッテリーでアップルのサプライヤー入りした事で一気に飛躍する土台ができる。
2005年TDKが約107億円でATLを買収。完全子会社化。アップル向けビジネスが安定してきた事が理由。
2011年12月、ATLの車載電池部門が分離・独立して「CATL(Contemporary Amperex Technology)」が誕生。
2017年日本のパナソニックを抜き、CATLが車載電池分野で世界シェアトップに。中国政府のサポートが背景にあり。
2018年世界の脱炭素化に向け、巨額投資が活性化。中国政府からの多額な補助金が入るようになる。以後、ダントツの市場トップシェアメーカーとなる。
CATLは中国内への投資だけではなく、世界的に投資を拡大。しかも、その規模が膨大であるため、これからもしばらくは業界を主導していく存在となるのは間違いない。
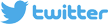










 SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移
トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移 強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い
強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い 東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移
東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移 マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況
マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況 現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移
現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移 ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数
ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数 TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移
TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移 楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移
楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移 NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況
NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況 Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移
ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移 Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移
Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移 フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移
フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移 ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率
ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率 任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数
任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数 日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移
日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移 インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移
インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移 BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移
BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況
Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況 メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率
メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率 LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況
LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況 キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明!
キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明! コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移
コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移 【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング
【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング 大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移
大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移 Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア
Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件
ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件 韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較
韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較 サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率
サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率 岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る
岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る