Foxconn Groupの連結決算:通年の売上推移
| 年度 | 売上高・収益 | 営業利益 [営業利益率(%)] |
純利益・最終損益 [純利益率(%)] |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 1兆4730億台湾ドル (5兆8920億円) |
266億台湾ドル (1064億円) [1.8%] |
551億台湾ドル (2204億円) [3.7%] |
| 2009年 | 1兆4205億台湾ドル | 247億台湾ドル [1.7%] |
756億台湾ドル [5.3%] |
| 2010年 | 2兆3131億台湾ドル | 354億台湾ドル [1.5%] |
771億台湾ドル [3.3%] |
| 2011年 | 2兆7733億台湾ドル | 315億台湾ドル [1.1%] |
815億台湾ドル [2.9%] |
| 2012年 | 3兆9053億台湾ドル | 1078億台湾ドル [2.8%] |
946億台湾ドル [2.4%] |
| 2013年 | 3兆9523億台湾ドル | 1093億台湾ドル [2.8%] |
1066億台湾ドル [2.7%] |
| 2014年 | 4兆2131億台湾ドル | 1431億台湾ドル [3.4%] |
1305億台湾ドル [3.1%] |
| 2015年 | 4兆4821億台湾ドル | 1642億台湾ドル [3.7%] |
1469億台湾ドル [2.9%] |
| 2016年 | 4兆3587億台湾ドル | 1749億台湾ドル [4.0%] |
1486億台湾ドル [3.4%] |
| 2017年 | 4兆7067億台湾ドル | 1125億台湾ドル [2.4%] |
1387億台湾ドル [2.9%] |
| 2018年 | 5兆2938億台湾ドル | 1361億台湾ドル [2.6%] |
1290億台湾ドル [2.4%] |
| 2019年 | 5兆3428億台湾ドル | 1148億台湾ドル [2.1%] |
1153億台湾ドル [2.2%] |
| 2020年 | 5兆3580億台湾ドル | 1108億台湾ドル [2.1%] |
1017億台湾ドル [1.9%] |
| 2021年 | 5兆9941億台湾ドル | 1489億台湾ドル [2.5%] |
1393億台湾ドル [2.3%] |
| 2022年 | 6兆6269億台湾ドル | 1738億台湾ドル [2.6%] |
1415億台湾ドル [2.1%] |
| 2023年 | 6兆1622億台湾ドル | 1665億台湾ドル [2.7%] |
1547億台湾ドル [2.5%] |
| 2024年 | 6兆8596億台湾ドル (27兆4384億円) |
2006億台湾ドル (8024億円) [2.9%] |
1716億台湾ドル (6864億円) [2.5%] |
平均利益率
- 傘下の業績推移
- シャープ連結(全体)
- シャープ「液晶パネル事業」
- EMS競合の業績推移
- ペガトロン
- クアンタ・コンピュータ
- コンパル・エレクトロニクス
- ウィストロン
会社の動向
- 鴻海精密工業(ホンハイせいみつこうぎょう)は「鴻海プラスチック工業」として1974年に設立。単に「ホンハイ」と言われたり、世界ブランド名の「フォックスコン(Foxconn)」と言われる。
- ホンハイはEMS世界トップ企業。EMSとは「Electronics Manufacturing Service」の略で、製造受託サービス企業のこと。例えば、iPhoneをアップルから請け負って代わりに製造する企業のこと。
- フォックスコンの従業員は130万人(2015年度)。この多くが中国工場で雇用する中国人。製造受託は、典型的な労働集約型のビジネスであり、「技術で勝負」というよりも「雇用管理」が勝負。
- 2008年から2021年の間で売上規模4倍。2007年から発売されたiPhoneの受託製造が売上を押し上げ。
- 台湾のEMS企業の多くは営業利益率2%未満だったりするが、ホンハイの営業利益率は同業他社と比較して高い。
- ホンハイの利益率が高い理由は、利幅が低い組み立て加工だけのビジネスではなく、部品生産なども手掛けるため。自社で供給できる製品量が多い事が利幅が高い理由。スマホに搭載されるカメラモジュールもホンハイや傘下のシャープが生産していたりする。
- 2013年頃からアップルのCEOティム・クックは、ホンハイ依存度を減らすため、台湾ペガトロンや台湾ウィストロンへの製造委託を増やしている。2014年度から2017年度にかけてホンハイの売上高が足踏み状態となっているのは、それが主な理由と思われる。
- 売上高は右肩上がりだが、これは受託製造しているiPhoneの製造原価が上がっている事も要因の一つ。例えば、ディスプレーは液晶から価格が高い有機ELパネルになっていたりしている。
- ホンハイは2022年時点で全体の75%の生産拠点が中国にあるとされる。そして政治的な事情や人件費高騰の問題があるため、中国依存から脱却を進め、インドへ一部の拠点を移す動きがある。しかし、ビジネス的に中国企業との関係を強化する動きもある。
- 任天堂スイッチやプレイステーションの受託生産も売上規模拡大につながっている。
- 2016年にシャープを買収。ホンハイとシャープの製造部門の合理化・相乗効果により、シャープの業績は安定化へ。
- 製造受託業界の市場規模は2020年度で57兆円。(これはEMSに分類される企業の売上高合計によるもの)。ホンハイの2020年度の売上高20兆8963億円は、売上高規模で業界36.6%のシェアとなる。
Foxconn Groupの財政・経営状況
| 年度 | 総資産 [現金・手元資金] |
負債総額 [有利子負債] |
自己資本・純資産 [自己資本比率(%)] |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 1兆1818億台湾ドル | 7109億台湾ドル | 4709億台湾ドル [39.8%] |
| 2015年 | 2兆3082億台湾ドル [6571億台湾ドル] |
1兆2479億台湾ドル [2422億台湾ドル] |
1兆603億台湾ドル [45.9%] |
| 2020年 | 3兆6742億台湾ドル [1兆2327億台湾ドル] |
2兆2001億台湾ドル [6797億台湾ドル] |
1兆4741億台湾ドル [40.1%] |
| 2021年 | 3兆9088億台湾ドル [1兆594億台湾ドル] |
2兆3356億台湾ドル [8219億台湾ドル] |
1兆5732億台湾ドル [40.1%] |
| 2022年 | 4兆1340億台湾ドル | 2兆4834億台湾ドル | 1兆6505億台湾ドル [39.9%] |
- 2010年以降、自己資本比率40%前後を規律として、安定的に資産規模を伸ばしている。財務ルールを守った安定成長は、郭台銘社長の経営哲学によるもの。
フォックスコンの主要顧客
- アップル……iPhone、iPad、ノートPC(MacBook)
- DELL……ノートパソコン、デスクトップPC、モニタ、サーバー。
- HP(ヒューレット・パッカード)……パソコン、モニタ、サーバー、印刷機器。
- Google……スマートフォン(Google Pixel)、サーバー。
- マイクソロソフト……Xbox、サーバー。
- Amazon……タブレット(Kindle)、サーバー。
- ソニー……プレイステーション、液晶テレビ。
- 任天堂……Nintendoスイッチ、3DS、Wiiなど
- 日米の大手企業から売上規模が大きい製品の受託生産をしているため、比例してホンハイの売上規模も大きくなる。
- アメリカ企業から受託生産しているサーバーの生産量が増加傾向。全世界のサーバーの約6割をフォックスコンが生産しているとされる。2022年度はサーバーだけで1兆台湾ドル(4兆円)以上の売上があった模様。
- 中国ファーウェイなども顧客だったが、アメリカからの制裁以降は縮小。
経済安全保障に直結
ホンハイがEMSという分野で巨額なビジネスに育てることができた理由は政治的な事情が大きい。
台湾は内需が小さく、さらに中国との対立もあるため、アメリカ企業や日本企業とはライバル関係というよりも「協力関係を築く」戦略があった。
そして、人件費高騰の問題を抱えていた先進国の電子製品を受託生産するビジネスに着目し、規模を拡大。結果、台湾には製造受託企業が集中する状況となり、半導体分野ではTSMCやUMCなどの半導体受託製造メーカー(ファウンドリー)も誕生。
そして、ホンハイの製造工場の多くが中国にあり、雇用不安定な中国の雇用をもたらしている状態。つまり、中国側が台湾企業に依存している状態。
中国にとっては台湾企業が他の国に出て行ってしまうと困るため、中国政府も下手な対応を取る事ができない。それが、台湾勢が中国に強気になれる理由。
そして、現在では台湾は世界の製造業で欠かせない存在となり、それが対立する中国から身を守る「経済安全保障」につながっている。実際にアメリカは「中国から台湾を守る」として、あからさまな動きに出ているが、その理由の一つが台湾にエレクトロニクス産業が集中している事があげられる。
2022年度のグローバル受託製造メーカーランキング
| 順位 | 企業名 売上高 |
営業利益 [営業利益率(%)] |
純利益・最終損益 [純利益率(%)] |
|---|---|---|---|
| 1位 | ホンハイ精密工業(台湾) 6兆6269億台湾ドル (26兆5076億円) |
1738億台湾ドル (6952億円) [2.6%] |
1415億台湾ドル (5660億円) [2.1%] |
| 2位 | ペガトロン(台湾) 1兆3176億台湾ドル (5兆2704億円) |
254億台湾ドル (1016億円) [1.9%] |
151億台湾ドル (604億円) [1.1%] |
| 3位 | クアンタ(台湾) 1兆2804億台湾ドル (5兆1216億円) |
312億台湾ドル (1248億円) [2.4%] |
290億台湾ドル (1160億円) [2.3%] |
| 4位 | ジェイビル(米国) 334.78億ドル (4兆3521億円) |
13.93億ドル (1811億円) [4.2%] |
9.96億ドル (1295億円) [3.0%] |
| 5位 | コンパル(台湾) 1兆732億台湾ドル (4兆2928億円) |
92億台湾ドル (368億円) [0.9%] |
73億台湾ドル (292億円) [0.7%] |
| 6位 | ウィストロン(台湾) 9846億台湾ドル (3兆9384億円) |
275億台湾ドル (1100億円) [2.8%] |
112億台湾ドル (448億円) [1.1%] |
| 7位 | フレックス(シンガポール) 260.41億ドル (3兆3853億円) |
9.72億ドル (1264億円) [3.7%] |
9.36億ドル (1217億円) [3.6%] |
- ホンハイはEMS業界でダントツの売上高トップ。ビジネスの性質上、利益率が低いが、売上高のボリュームが大きいため、それなりのお金が会社に残る。
- 利益率を高めるため、ホンハイを含むすべてのEMS企業は人間の代わりとなるロボットを導入して、工場自動化を進めている。
- 台湾企業5社の売上高を合計すると日本円で約45兆円。世界のエレクトロニクス産業の市場規模が200~250兆円と言われるため、おおまかに言えば業界全体の18~22%の製造部門を台湾EMSメーカー5社が担っている事になる。
- その台湾勢5社以外にも、イノラックス、インベンテック、TPVテクノロジーなど、日本円で1兆円以上の売上高をもつEMS企業が存在。受託製造分野は「台湾のビジネス」だと言っていいレベル。
意外にも参入障壁が高い
フォックスコンを含む製造受託業界は、どんな企業でも参入できるように見えて、実は参入障壁が高いという事実がある。理由は以下。
- 台湾EMS企業の営業利益率は2%前後が目安。利益率が低いビジネスであるため、参入してもあまり儲からない。そのため新規参入企業が少ない。
- 利益が低いので小規模ビジネスは難しい。しかし規模を大きくするとなると生産性の高い巨大工場を所有する必要があり、コストがかかる。
- 製品を組み立てるための多くの従業員を雇用する必要がある。つまり、市況の変化によるリストラなどの人的な管理が難しい。
- すでに既存の大手企業だけでも競争が激しい。
- 顧客との信頼関係をつくるのが難しい。例えば、中国企業は政治的な事情で米国製品を受注する事は難しい。
「下請け」だとか「組み立て業」などと軽視する人も多いが、この製造受注ビジネスはかなり難しい経営判断が求められる。だからこそ参入が難しい。この分野では今後も台湾勢が占有的で絶対的な地位を維持していく事になる。
多角化を目指す
スマートフォンやパソコンは成長に伸びしろがないため、ホンハイは単純な製造請負以外のビジネスを増やす動きがある。簡単に言えば「多角化」だが、その動きが以下。
2016年ノキアの携帯電話事業を買収。
2018年東芝のPC事業(dynabook:ダイナブック)を買収。
世界中の企業から、パソコンやスマホ、プリンタなどの製造を請け負っているホンハイが、パソコンやスマホなどの完全自社製品のビジネスを拡大。
これは製造受託企業として、顧客とライバル関係になるということであり、信頼関係を損ねる問題がある。例えば、DELLのパソコンとホンハイのダイナブックが競合になるとDELLはホンハイから離れていくことになったりする。
ビジネス規模が大きくなると、顧客との関係性が難しくなるが、ホンハイは大口顧客と対立関係にならないレベルの生産量で事業を行う見通し。
電気自動車の「製造」へ参入
ホンハイは、受託製造メーカーとしてEV(電気自動車)分野にも参入表明。世界中の自動車関連会社に呼びかけ、サプライチェーン構築に急いでいる。
ホンハイとの共同開発に100社ほどの日本企業が参加。トヨタ系のデンソーの他、中核部品であるモーターにおいてはニデック(日本電産)と提携し、共にEVの開発を進めていく見通し。
他社の自動車を受託生産するとなると、トヨタで言えば「86」や「スープラ」といった少量生産車の受託生産が中心になると思われる。
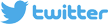




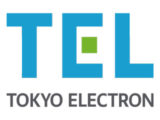





 SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移
トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移 強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い
強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移
テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移 東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移
東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移 マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況
マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況 現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移
現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移 ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数
ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数 楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移
楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移 NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況
NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況 Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移
ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移 Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移
Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移 フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移
フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移 ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率
ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率 任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数
任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数 日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移
日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移 インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移
インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移 BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移
BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況
Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況 メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率
メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率 LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況
LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況 キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明!
キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明! コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移
コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移 【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング
【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア
Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件
ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件 韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較
韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較 サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率
サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率 岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る
岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る