スポンサーリンク
Texas Instrumentsの連結決算:通年の売上推移
| 年度 | 売上高・収益 | 営業利益 [営業利益率(%)] |
純利益・最終損益 [純利益率(%)] |
|---|---|---|---|
| 2003年 | 98.34億ドル | 9.65億ドル [9.8%] |
11.98億ドル [12.2%] |
| 2004年 | 125.80億ドル | 22.07億ドル [17.5%] |
18.61億ドル [14.8%] |
| 2005年 | 133.92億ドル | 27.91億ドル [20.8%] |
23.24億ドル [17.4%] |
| 2006年 | 142.55億ドル | 33.67億ドル [23.6%] |
43.41億ドル [30.5%] |
| 2007年 | 138.35億ドル | 34.97億ドル [25.3%] |
26.57億ドル [19.2%] |
| 2008年 | 125.01億ドル | 24.37億ドル [19.5%] |
19.20億ドル [15.4%] |
| 2009年 | 104.27億ドル | 19.91億ドル [19.1%] |
14.70億ドル [14.1%] |
| 2010年 | 139.66億ドル | 45.14億ドル [32.3%] |
31.48億ドル [22.5%] |
| 2011年 | 137.35億ドル | 29.92億ドル [21.7%] |
22.01億ドル [16.0%] |
| 2012年 | 128.25億ドル | 19.73億ドル [15.3%] |
17.28億ドル [13.5%] |
| 2013年 | 122.05億ドル | 28.32億ドル [23.1%] |
21.25億ドル [17.4%] |
| 2014年 | 130.45億ドル | 39.47億ドル [30.2%] |
27.77億ドル [21.3%] |
| 2015年 | 130.00億ドル | 43.22億ドル [33.2%] |
29.86億ドル [22.9%] |
| 2016年 | 133.70億ドル | 48.55億ドル [36.3%] |
35.95億ドル [26.9%] |
| 2017年 | 149.61億ドル | 60.83億ドル [41.1%] |
36.48億ドル [24.3%] |
| 2018年 | 157.84億ドル | 67.13億ドル [42.5%] |
55.37億ドル [35.1%] |
| 2019年 | 143.83億ドル | 57.23億ドル [39.8%] |
49.85億ドル [34.7%] |
| 2020年 | 144.61億ドル | 58.94億ドル [40.7%] |
55.68億ドル [38.5%] |
| 2021年 | 183.44億ドル | 89.60億ドル [48.8%] |
77.36億ドル [42.1%] |
| 2022年 | 200.28億ドル | 101.40億ドル [50.6%] |
87.09億ドル [43.5%] |
| 2023年 | 170.19億ドル | 73.31億ドル [43.1%] |
65.10億ドル [38.2%] |
| 2024年 | 156.41億ドル | 54.65億ドル [34.9%] |
47.99億ドル [30.7%] |
出所:Texas Instruments。本決算期は12月末。
スポンサーリンク
平均利益率
テキサス・インスツルメンツの2003年から2024年までの営業利益率の平均が30.5%。
会社の動向
- テキサス・インスツルメンツ(略称:TI)は1930年にGeophysical Service社として設立されたアメリカの半導体メーカー。アナログ半導体に強みをもつ。
- 1950年に世界初のシリコン型トランジスタを製品化。半導体産業の基礎をもたらした老舗企業。
- 世界14か所に工場をもつ。300mmウエハー工場は14工場のうち2工場。2工場ともテキサス州。(2022年時点)
- 日本では1960年代から営業拠点をもち、生産工場もあり。日本国内の生産工場は、福島県(会津若松市)と茨城県(美浦村)に200mmファブをもつ。(2022年時点)。
- 1990年代までは総合半導体メーカーだった。ロジック、メモリ(DRAM)、アナログ半導体など多くの製品を手掛けていた。
- 1998年に選択と集中により、収益性が悪化していたDRAMから撤退。メモリ事業はマイクロン(米国)に売却。
- 2000年頃までは選択と集中が進んでいなかった事から営業利益率が10%未満だった年が多く、赤字を出すこともあった。
- 2013年以降は利益率が40%を超えるようになっているが、2012年に買収したナショナル・セミコンダクターとの相乗効果が大きいとされる。
- アナログ半導体分野で豊富な製品ポートフォリオをもつ。顧客とのビジネスも有利に進む事が高利益率の理由の一つ。
- TIの自社工場で製造する半導体のうち、80%がアナログ半導体。製品全体の80%が自社工場生産。残りの20%が台湾のTSMCやUMCなどのファウンドリーへ委託。(2022年時点)
- 全体の売上構成は、アナログ製品が70%、残りの約30%がMCUなどの組み込みプロセシング製品。(2022年時点)
スポンサーリンク
国・地域ごとの収益内訳
| 年度 | アメリカ | 中国 | アジア | 欧州・中東 アフリカ |
日本 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億ドル) | ||||||
| 2015年 | 16.12 | 79.10 | 26.13 | 11.27 | 1.88 | |
| 2016年 | 16.82 | 80.24 | 23.93 | 10.40 | 2.31 | |
| 2017年 | 19.01 | 88.24 | 29.07 | 10.49 | 2.80 | |
| 2018年 | 22.88 | 92.40 | 30.47 | 8.69 | 3.40 | |
| 2019年 | 18.27 | 86.50 | 27.07 | 7.96 | 4.03 | |
| 2020年 | 15.47 | 95.41 | 22.49 | 7.34 | 3.90 | |
| 2021年 | 19.06 | 121.85 | 28.02 | 9.59 | 4.92 | |
| 2022年 | 66.09 | 48.07 | 20.03 | 48.07 | 16.02 | 2.00 |
| 2023年 | 58.14 | 32.93 | 17.21 | 46.42 | 17.82 | 2.67 |
| 2024年 | 59.57 | 30.12 | 16.81 | 35.19 | 12.12 | 2.60 |
| 2025年 | ||||||
出所:Texas Instruments。単位は億ドル。
- 全体的に自働車産業やスマートフォンなどの製造が活発な国・地域への売上が多い。
- テキサスが得意とするアナログIC。その国産化を進める中国の台頭により、売上高の伸び悩みが懸念される。
スポンサーリンク
アナログ半導体の売上シェア
| 順位 | 1995年 | 2015年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| メーカー [市場シェア(%)] |
|||
| 1位 | STマイクロ(スイス) | テキサス(米国) [18%] |
テキサス(米国) [19%] |
| 2位 | フィリップス(オランダ) | インフィニオン(ドイツ) [6%] |
アナログ・デバイセズ(米国) [9%] |
| 3位 | ナショナルセミ(米国) | スカイワークス(米国) [6%] |
スカイワークス(米国) [7%] |
| 4位 | モトローラ(米国) | アナログ・デバイセズ(米国) [6%] |
インフィニオン(ドイツ) [7%] |
| 5位 | テキサス(米国) | STマイクロ(スイス) [5%] |
STマイクロ(スイス) [6%] |
| 6位 | 東芝(日本) | マキシム(米国) [4%] |
NXPセミ(オランダ) [4%] |
| 7位 | 三洋電機(日本) | NXPセミ(オランダ) [4%] |
マキシム(米国) [4%] |
| 8位 | アナログ・デバイセズ(米国) | リニア・テクノロジー(米国) [3%] |
オンセミ(米国) [3%] |
| 9位 | シーメンス(ドイツ) | オンセミ(米国) [2%] |
マイクロチップ(米国) [2%] |
| 10位 | NEC(日本) | ルネサス(日本) [2%] |
ルネサス(日本) [2%] |
出所:1995年はガートナー、2015年~2020年はIC Insights。
- 1995年に業界5位だったテキサスは、2011年に同業National Semiconductor(ナショナル・セミコンダクター)を買収。それにより生産量と製品ラインナップが拡充し、2020年度は市場シェア19%でダントツのトップシェアへ。
- アナログIC業界は、設備投資費が最先端ロジック/メモリのように高額になる事はなく、製品も多品種なので、小規模でもそれなりにビジネスを続けることができる。そのため、多くの企業でシェアを分け合っているような状況。そして、上位メーカーはアメリカやヨーロッパ、日本などの先進国の半導体メーカーばかりが並ぶ。
- 韓国勢や台湾勢が入り込めていないのは、アナログ分野は設計や経営的にも難しく、技術や信頼、ポートフォリオが蓄積されるまで時間がかかるため。また、先進国の古参メーカーが乱立し、競争が激しいため参入しても利益がでない事も理由。
- なお、日本企業はルネサス・エレクトロニクスが世界シェア2%で10位に入る。なお、アナログ半導体を手掛ける日本企業の売上を合計すると世界シェア約10%ほどある。
絶対的な理由
アナログICは多品種であるため急成長が難しい。例えば、サムスンはDRAMにおいて1980年代初頭に本格注力し、約10年後の1992年にトップシェアになったが、アナログICはDRAMのように規格化された製品を一気に量産すれば良いビジネスではない。
そして、アナログ分野はデジタル半導体のような「0」と「1」だけの世界ではなく、「あいまい」な世界だったりする。そのため、回路設計においても難しさがつきまとう。優秀な人材も短期間では育たない。
そのアナログ分野で、テキサス・インスツルメンツが評価される理由は以下。
- TIは、1950年に世界初のシリコン型トランジスタを製品化。半導体開発において長い歴史をもつ名門企業。優秀なエンジニアが長い歳月をかけてつくりあげてきた英知が製品に刻まれており、それが業界で認識されている。
- 多くの企業はテキサスと長く取引をしており、慣性的に製品を使い続けている。
- 電子企業はテキサスの製品に信頼を持っているので、他のアナログ製品が必要となれば「次もテキサスに」となる。同じメーカー製品を揃えた方が相性が良く、不具合がないため、TI製品の採用が広がっていく。
- テキサスも製品ラインナップが幅広いので、顧客が必要な製品を用意できる。
車載向けマイコンにも強み
自動車向けマイクロコントローラー(マイコン)市場においてもテキサス・インスツルメンツは約10%ほどのシェアをもっている。以下は2020年のデータ。
| 順位 | 企業 | 国 | 市場シェア(%) |
|---|---|---|---|
| 1位 | ルネサス・エレクトロニクス | 日本 | 26.7% |
| 2位 | NXPセミコンダクターズ | オランダ | 26.3% |
| 3位 | インフィニオン | ドイツ | 16.9% |
| 4位 | テキサス・インスツルメンツ | アメリカ | 9.8% |
| 5位 | マイクロチップ・テクノロジー | アメリカ | 6.9% |
出所:インフィニオンの決算報告書より引用。
- テキサスは自動車向け半導体をさらに強化中。
- マイコン分野は日本のルネサスが業界トップシェア。ルネサスの顧客はトヨタ、ホンダ、日産などの日系メーカーが中心。
日本のアナログ半導体は再編が加速
日本企業の中にはアナログ半導体事業をもっている会社が多いが、スケールメリットが必要なハイテク業界では必然的に再編や事業強化が進んでいる模様。
- 2021年1月、日清紡HDは連結子会社の新日本無線とリコー電子デバイスの2社を統合すると発表。新社名は「日清紡マイクロデバイス」
- ジャパンセミコンダクター(東芝グループ)は、車載向けを中心にアナログ製品を強化中。また、月産能力10万枚の生産ラインで製造受託ビジネスも拡大していく模様。
- ルネサスもアナログデバイスに強い欧米企業を次々と買収し、ラインナップ強化中。
- 2019年、ミネベアミツミはエイブリック(SEIKOの子会社)を完全子会社化。
- 2016年、トレックス・セミコンダクターはフェニテックセミコンダクターを完全子会社化。車載向けに強いファブレスメーカーが工場所有することに。電源ICが中核。
日本企業のアナログ半導体の売上高をすべて合わせると、世界シェア10%を持っているとされる。上手く再編・統合して世界シェア上位に入る企業の登場に期待。
Texas Instrumentsの財政・経営状況
| 年度 | 総資産 [現金・手元資金] |
負債総額 [有利子負債] |
自己資本・純資産 [自己資本比率(%)] |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 150.63億ドル [12.19億ドル] |
31.26億ドル [6.61億ドル] |
119.37億ドル [79.2%] |
| 2010年 | 134.01億ドル [13.19億ドル] |
29.64億ドル [なし] |
104.37億ドル [77.9%] |
| 2015年 | 162.30億ドル [32.18億ドル] |
62.84億ドル [41.20億ドル] |
99.46億ドル [61.3%] |
| 2020年 | 193.51億ドル [65.68億ドル] |
101.64億ドル [67.98億ドル] |
91.87億ドル [47.5%] |
| 2021年 | 246.76億ドル [97.39億ドル] |
113.43億ドル [77.41億ドル] |
133.33億ドル [54.0%] |
| 2022年 | 272.07億ドル [90.67億ドル] |
126.30億ドル [87.35億ドル] |
145.77億ドル [53.6%] |
| 2023年 | 323.48億ドル [85.75億ドル] |
154.51億ドル [112.23億ドル] |
168.97億ドル [52.2%] |
- 株主還元がとてつもないので、爆発的な利益を出し続けているわりに、あまりお金が会社に残らない。アップルと同じ。
連結社員数と研究開発投資について
| 年度 | 従業員数(連結) | 設備投資費 | 研究開発費 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 28400人 | – | 15.70億ドル |
| 2015年 | 29900人 | – | 12.67億ドル |
| 2020年 | 30000人 | – | 15.30億ドル |
| 2022年 | 33000人 | 42億ドル | 16.70億ドル |
出所:テキサス・インスツルメンツ
- 2011年にアナログICに強みをもつNational Semiconductorを買収し、従業員数が34700人に増加したが、数年かけて雇用調整(リストラ)を決行。2015年には買収前と同等の従業員数(29900人)に戻った。半導体需要の拡大期でも厳格な経営判断がある。
スポンサーリンク
関連記事
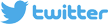










 SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移
トヨタの販売台数の推移と売上高・営業利益率・純利益の推移 強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い
強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移
テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移 東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移
東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移 マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況
マイクロソフトの業績推移:売上・営業利益率・純利益・財務状況 現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移
現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移 ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移
ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数
ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数 TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移
TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移 楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移
楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移 NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況
NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況 Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移
ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移 Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移
Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移 フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移
フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移 ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率
ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率 任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数
任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数 日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移
日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移 インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移
インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移 BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移
BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況
Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況 メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率
メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率 LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況
LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況 キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明!
キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明! コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移
コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移 【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング
【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング 大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移
大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移 Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア
Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件
ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件 韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較
韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較 サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率
サムスンの半導体装置会社SEMESの業績推移:売上高・営業利益率 岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る
岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る