スポンサーリンク
Panasonicの連結決算:通年の売上推移
| 年度 | 売上高・収益 | 営業利益 [営業利益率(%)] |
純利益・最終損益 [純利益率(%)] |
|---|---|---|---|
| 1998年 | 7兆6401億円 | 1936億円 [2.5%] |
135億円 [0.2%] |
| 1999年 | 7兆2993億円 | 1590億円 [2.2%] |
997億円 [1.4%] |
| 2000年 | 7兆6815億円 | 1884億円 [2.5%] |
415億円 [0.5%] |
| 2001年 | 6兆8766億円 | -2118億円 [-3.1%] |
-4310億円 [-6.3%] |
| 2002年 | 7兆4017億円 | 1266億円 [1.7%] |
-195億円 [-0.3%] |
| 2003年 | 7兆4797億円 | 1955億円 [2.6%] |
421億円 [0.6%] |
| 2004年 | 8兆7136億円 | 3085億円 [3.5%] |
585億円 [0.7%] |
| 2005年 | 8兆8943億円 | 4143億円 [4.7%] |
1544億円 [1.7%] |
| 2006年 | 9兆1082億円 | 4595億円 [5.0%] |
2172億円 [2.4%] |
| 2007年 | 9兆689億円 (テスラと提携) |
5194億円 [5.7%] |
2818億円 [3.1%] |
| 2008年 | 7兆7655億円 | 728億円 [0.9%] |
-3789億円 [-4.9%] |
| 2009年 | 7兆4179億円 | 1904億円 [2.5%] |
-1034億円 [-1.4%] |
| 2010年 | 8兆6926億円 | 3052億円 [3.5%] |
740億円 [0.9%] |
| 2011年 | 7兆8462億円 (4月 三洋電機を完全子会社化) |
437億円 [0.6%] |
-7722億円 [-9.8%] |
| 2012年 | 7兆3030億円 | 1609億円 [2.2%] |
-7543億円 [-10.3%] |
| 2013年 | 7兆7365億円 | 3051億円 [3.9%] |
1204億円 [1.6%] |
| 2014年 | 7兆7150億円 | 3819億円 [5.0%] |
1795億円 [2.3%] |
| 2015年 | 7兆6263億円 | 2303億円 [3.0%] |
1652億円 [2.2%] |
| 2016年 | 7兆3437億円 | 2768億円 [3.8%] |
1494億円 [2.0%] |
| 2017年 | 7兆9821億円 | 3805億円 [4.8%] |
2360億円 [3.0%] |
| 2018年 | 8兆27億円 | 4114億円 [5.1%] |
2841億円 [3.6%] |
| 2019年 | 7兆4906億円 | 2937億円 [3.9%] |
2400億円 [3.2%] |
| 2020年 | 6兆6987億円 | 2586億円 [3.9%] |
1839億円 [2.7%] |
| 2021年 | 7兆3887億円 | 3575億円 [4.8%] |
2553億円 [3.5%] |
| 2022年 | 8兆3789億円 (4月 持株会社へ移行) |
2886億円 [3.4%] |
2655億円 [3.2%] |
| 2023年 | 8兆4964億円 | 3609億円 [4.2%] |
4439億円 [5.2%] |
| 2024年 | 8兆4581億円 | 4264億円 [5.0%] |
3662億円 [4.3%] |
出所:Panasonic
スポンサーリンク
平均利益率
パナソニックの1998年から2024年までの営業利益率の平均が3.2%。
- グループ会社の業績推移
- パナソニック(家電事業)
- パナソニックエナジー
会社の動向
- パナソニックは、松下電器産業として1935年設立。
- 2001年は、営業損失(-2118億円)、最終赤字(-4310億円)。ITバブル崩壊と言われる時期で、パナソニックにおいてもIT関連、パソコン、部品関連、携帯電話市場の不振が影響。「創業以来の大赤字」と言われた。
- 2001年度以外は営業利益で赤字を出していない。
- 2008年から2012年までは最終利益が黒字化しなかった。アメリカ発の金融危機、ユーロ危機、円高、東日本大震災など、様々な不運がある中で、さらに三洋電機の買収と再編においても多額のコストを計上。
- 2008年度から2012年度までの最終損失の合計が-1兆9348億円。財務が急激に悪化。
- 今後のパナソニックは、年間利益5000億円の目標を宣言。持株会社となり、それぞれの事業会社が厳格な数値目標を掲げて利益を出していく見込み。
スポンサーリンク
Panasonicの財政・経営状況
| 年度 | 総資産 [現金・手元資金] |
負債総額 [有利子負債] |
自己資本・純資産 [自己資本比率(%)] |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 7兆9646億円 [1兆6673億円] |
4兆1770億円 [6039億円] |
3兆7876億円 [47.6%] |
| 2010年 | 7兆8228億円 [9748億円] |
4兆8765億円 [1兆5952億円] |
2兆9463億円 [37.7%] |
| 2015年 | 5兆5969億円 [1兆142億円] |
3兆7426億円 [7259億円] |
1兆8543億円 [33.1%] |
| 2020年 | 6兆8470億円 [1兆5932億円] |
4兆785億円 [1兆1376億円] |
2兆7685億円 [40.4%] |
| 2021年 | 8兆235億円 [1兆2058億円] |
4兆6764億円 [1兆6306億円] |
3兆3471億円 [41.7%] |
| 2022年 | 8兆595億円 [8195億円] |
4兆2695億円 [1兆4571億円] |
3兆7900億円 [47.0%] |
| 2023年 | 9兆4111億円 [1兆1196億円] |
4兆6892億円 [1兆3641億円] |
4兆7219億円 [50.2%] |
出所:Panasonic
- 2005年と2020年を比較すると、資産規模が縮小。リストラを行った事が要因。三洋電機を取り込んでも結果的に会社規模が大きくならなかった。
- 製造業は自己資本比率40%以上が一つの目安。パナソニックの財務規律も40%以上を意識。
- 2008年から2012年まで合計約2兆円近くの最終損失を出しているが、あらゆる改革のもとで現在の財務は安定的。
- バッテリー事業拡大に向けた巨額資金が必要になるため、やはり潜在的な不安がある。以前に保有していた半導体工場や液晶パネル工場などと同様に、多くの工場を抱えるのは市況の変化によるリスクがつきまとう。
Panasonicの連結社員数と開発投資について
| 年度 | 従業員数(連結) | 平均年収 | 設備投資額 | 研究開発額 |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 33万4402人 | 798万円 | 3458億円 | 5648億円 |
| 2010年 | 36万6937人 | 778万円 | 4038億円 | 5278億円 |
| 2015年 | 24万9520人 | 789万円 | 2488億円 | 4498億円 |
| 2020年 | 24万3540人 | 744万円 | 2310億円 | 4198億円 |
| 2023年 | 22万8420人 | 930万円 | 5680億円 | 4912億円 |
出所:Panasonic
- 2005年と2020年を比較すると、従業員は9万862人減少。約27%減。
- 2020年度の平均年収が744万円。90862人×744万円=6760億円。パナソニックは改革によって、2005年との比較で約6760億円の人件費(固定費)を削減。
- ディスプレイパネル生産や半導体事業などからの撤退による人員削減だけではなく、全体的に従業員数をスリム化。2009年に三洋電機を買収したが、結局は従業員が減少。
- 創業者の松下幸之助による「社員をリストラしない」「社員は守る」という経営哲学により、時代が変わってもリストラを先送りしてきたところがあるが、リーマンショック以降の大赤字により、松下幸之助の哲学は否定されるようになった。
- 松下幸之助の経営哲学は、性善説が通用した高度経済成長時代がベース。時代が変わったため仕方がない。
- 設備投資費について、近年はエナジー事業(バッテリー部門)の投資が増えている。2023年度はパナソニックエナジーのみで2921億円を計上。
スポンサーリンク
Panasonicの国内/外国への収益割合
| 年度 | 日本 | 米大陸 | 欧州 | アジア | 中国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 51.8% | 15.6% | 12.5% | 12.4% | 7.6% |
| 2010年 | 51.9% | 12.3% | 9.9% | 12.3% | 13.6% |
| 2015年 | 47.2% | 16.3% | 9.2% | 13.7% | 12.6% |
| 2020年 | 46.5% | 16.7% | 9.9% | 14.1% | 12.9% |
| 2023年 | 40.1% | 25.0% | 11.5% | 13.9% | 9.5% |
出所:Panasonic
- 日本向けへの売上比率が減少し、海外売上比率が増加。日本のグローバル企業の典型的な形だが、パナソニックの場合は日本向けの売上高の減少で、海外売上比率が上昇。これはディスプレイ関連やモバイルなどの製造関連が衰退している事が要因。
- アメリカ向けの売上が増えている事が希望。
売上内訳:セグメント別の業績
| 事業 | 2020年/売上高 [営業利益/利益率(%)] |
2021年/売上高 [営業利益/利益率(%)] |
|---|---|---|
| くらし事業 (家電・エアコン等) |
3兆5489億円 [1669億円/4.7%] |
3兆6476億円 [1136億円/3.1%] |
| オートモーティブ (車載機器等) |
1兆171億円 [-118億円/-1.1%] |
1兆671億円 [13億円/0.1%] |
| コネクト (企業向けシステム) |
8180億円 [-200億円/-2.4%] |
9249億円 [517億円/5.6%] |
| インダストリー (部品/産業機器) |
9846億円 [407億円/4.1%] |
1兆1314億円 [832億円/7.3%] |
| エナジー (バッテリー・乾電池) |
6000億円 [335億円/5.6%] |
7644億円 [642億円/8.3%] |
出所:Panasonic

- くらし事業(家電事業)……世界1位~2位を目指すと宣言。部品の共同調達で従来よりもコスト削減を目指す。また、空調(エアコン)や冷蔵庫、洗濯機などの成長率や利益率が高い分野に注力。
- オートモーティブ(自動車関連)……世界のEV化の成長を取り込む見込み。
- コネクト(企業向けシステム)……買収した米国ブルーヨンダーからの安定収入。そして、自社がもつセンサー機器とソフトを融合した商品で顧客拡大を目指す。
- インダストリー(産業機器・電子部品)……採算が悪い事業を排除して得意分野を伸ばす。
- エナジー(バッテリー事業)……自動車EV市場拡大に向け、中国CATLや韓国LGエナジーと共に市場トップ3を維持したいところ。テンションが高いテスラと協業関係にあるのが強み。
M&A・合弁・再編の動向
2011年三洋電機を完全子会社化。この時期、売上高10兆円を目指すと発表。
2011年買収した三洋電機の白物家電事業のうち冷蔵庫・洗濯機部門を中国の家電大手ハイアールに約100億円で売却。
2013年プラズマディスプレイパネル生産から撤退。プラズマテレビ生産も撤退。生産と販売は液晶テレビに一本化。
2014年テスラと車載向けバッテリーで提携強化。アメリカで工場建設へ。
2016年アメリカの業務用冷蔵庫トップのハスマンを買収。
2017年パナホームを完全子会社化。社名をパナソニックホームへ。
2019年トヨタと自動車向けバッテリー合弁会社「プライム・プラネット・エナジー&ソリューションズ(PPES)」の設立。
2019年トヨタと住宅事業を統合。プライムライフテクノロジーズ誕生。
2020年半導体事業から撤退。工場は台湾Winbond Electronics傘下企業へ売却。
2021年アメリカのサプライチェーン管理サービス企業「ブルーヨンダー」を約8600億円で買収。既存事業との相乗効果を見込めるサブスクビジネスを確保。
2021年液晶パネル生産から撤退。姫路工場はバッテリー生産工場に生まれ変わる。
2022年持株会社体制へ移行。
スポンサーリンク
関連記事
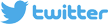










 SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
SONYの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
サムスン電子の業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い
強がる者と利用する者、北朝鮮と韓国の違い テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移
テスラの業績推移:EV販売台数・売上高・営業利益率・財務の推移 東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移
東芝~キオクシアの半導体売上高・営業利益・純利益・利益率の推移 現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移
現代・起亜(ヒョンデ・キア)の販売台数・売上高・営業利益の推移 ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移
ホンダの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数
ユニクロ・GU/ファストリの業績推移:売上高・利益率・店舗数 TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移
TSMCの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・シェアの推移 楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移
楽天の業績推移:売上高・営業利益率・財務・有利子負債の推移 NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況
NVIDIA(エヌビディア)の業績推移:売上・営業利益率・財務状況 Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移
Appleの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・総資産の推移 SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移
SKハイニックスの業績推移:売上高・営業利益率・純利益の推移 ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移
ルネサスエレクトロニクスの業績推移:売上・営業利益率の推移 Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移
Amazonの業績推移:売上高・営業利益率・純利益・財務状況の推移 フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移
フォルクスワーゲンの販売台数・売上高・営業利益・純利益の推移 ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率
ダイソー・セリア・キャンドゥ・ワッツの業績推移:売上高・利益率 任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数
任天堂の業績推移:売上高・営業利益率・ゲーム機/ソフト販売数 日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移
日産の業績推移:販売台数・売上高・営業利益率・財務状況の推移 インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移
インテル設立からの業績推移:売上高・営業利益率・財務の推移 BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移
BMWの業績推移:車/バイク販売台数・売上高・営業利益率の推移 Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況
Netflix(ネットフリックス)の業績推移:売上・利益率・財務状況 メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率
メルセデス・ベンツの業績推移:販売台数・売上高・営業利益率 LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況
LGエレクトロニクスの業績推移:売上高・営業利益率・財務状況 キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明!
キオクシアの利益率がサムスンより1.7倍以上高い事が判明! コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移
コストコの業績推移:売上高・営業利益率・有料会員数の推移 【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング
【2024年】世界自動車メーカー販売台数・売上・利益率ランキング 大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移
大韓航空の業績推移:売上高・営業利益率・財務状況の推移 Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア
Apple・サムスン・中国企業の東南アジアのスマホシェア ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件
ミヤネ屋にてアンミカの北朝鮮批判が冷酷で無責任すぎた件 韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較
韓国で子供の運動能力が低下!小中高生の50m走を日本と比較 岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る
岸田首相、韓国で詐欺映画パラサイト半地下のような写真を撮る